
日本では、様々な業種において、人手不足が進んでいます。
そこで活躍しているのが、特定技能外国人ですが、
特定技能には1号・2号はあり、その違いについて知っておく必要があります。
本記事では、特定技能1号・2号の違い、
2号への切り替えした場合のメリットや費用、補助金について、詳しく解説します。
特定技能とは何か?

特定技能とは、日本人の人材不足を補うために設置された在留資格です。
著しく労働者不足が発生している業種・職種で、
外国人も正社員として採用するため2019年4月に設置されました。
特定技能の資格を有するためには、最低限の知識と日本語力が必要です。
特定技能の資格を持った外国人は急増しており、
2024年6月末時点で25万人超えとなっています。
特定技能には「1号」と「2号」の種別があり、
特定技能1号を5年修了すると2号に移行することができ、
永続的に雇用することができます。
ただ、特定技能の自動車運送業に関しては1号しか認められていないため、
通算で最大5年までしか雇うことができませんので注意が必要です。
特定技能1号と2号の主な違い
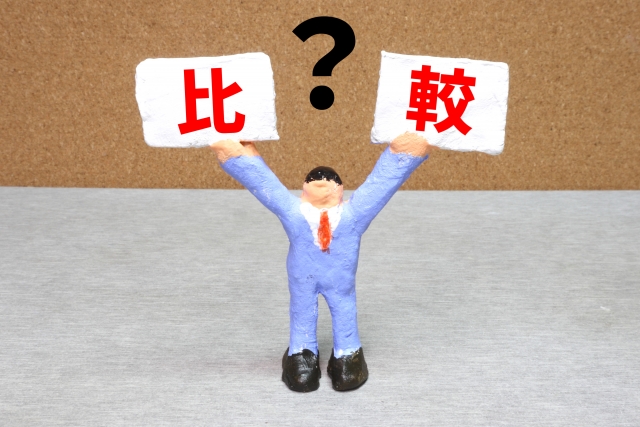
特定技能1号と2号では、以下のような違いがあります。
|
|
1号 |
2号 |
|
スキルレベル |
基本的業務を担う |
より高度な専門技術が必要 |
|
試験 |
基礎的な試験に合格 |
実務試験と専門試験に合格 |
|
求められる能力 |
即戦力としての基礎的能力 |
専門的な技術力 |
特定技能1号は特定技能2号より、スキルレベルが高く、
難易度の高い試験に合格しなければなりません。
つまり特定技能2号の方が、1号より高度な専門技術が必要です。
企業は採用時に適切なスキルレベルを持って
人を採用することが職場のパフォーマンス向上につながります。
特定技能2号の人を雇うと、特定技能2号の人より人件費がかかりますが、
2号のようにスキルレベルが高い場合、業務が効率的に行なわれることから、
長期的な視点で投資回収が可能です。
特定技能外国人が転職できる職種は、以下の16の産業・業種となっています。
|
①建設 |
⑨外食業 |
|
②造船・舶用工業 |
⑩素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
|
③自動車整備 |
⑪介護 |
|
④航空 |
⑫ビルクリーニング |
|
⑤宿泊 |
⑬自動車運送業 |
|
⑥農業 |
⑭鉄道 |
|
⑦漁業 |
⑮林業 |
|
⑧飲食料品製造業 |
⑯木材産業 |
1号・2号は、同じ業種に就職することができますが、
介護分野については1号のみに設定されており、2号には設定されていません。
1号と2号のそれぞれの必要書類と取得方法

特定技能1号・2号のそれぞれの必要書類と取得方法についてみていきましょう。
特定技能1号の必要書類と取得方法
まずは、特定技能1号からご紹介します。
特定技能1号の必要書類
特定技能1号の必要書類は以下の通りです。
|
必要書類 |
留意事項 |
|
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |
外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |
|
在留資格変更許可申請書 |
※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |
|
特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
|
特定技能雇用契約書の写し |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
|
雇用条件書の写し |
|
|
賃金の支払 |
|
|
雇用の経緯に係る説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
|
徴収費用の説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
|
健康診断個人票 |
病院発行の様式でも差し支えないが、 受診項目は参考様式に記載のものが含ま れていることが必要 外国語で作成されている場合は、日本 語訳を添付 |
|
受診者の申告書 |
- |
|
申請人の個人住民税の課税証明書 |
1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |
|
申請人の住民税の納税証明書 |
|
|
申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |
複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |
|
申請人の国民健康保険被保険者証の写し |
申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |
|
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |
|
|
次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |
申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |
|
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |
前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |
|
公的義務履行に関する誓約書 |
- |
|
1号特定技能外国人支援計画書 |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
|
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 |
- |
|
二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 |
対象の国籍は、カンボジア、タイ、ベ トナム(令和4年3月現在) |
出典:法務省「特定技能1号」に係る提出書類一覧表」参照
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の取得方法は、以下のようになっています。
①18歳以上であること
②特定産業分野の業務区分に対応する試験に合格すること
③日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)4級に合格すること
特定技能1号は、上記を満たしてから取得することが可能です。
特定技能2号の必要書類と取得方法
次に、特定技能2号の必要書類と取得方法についてみていきましょう。
特定技能2号の必要書類
特定技能2号の必要書類は以下の通りです。
|
必要書類 |
留意事項 |
|
特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表 |
外国人について同時に申請する場合 は、「申請する特定技能外国人の名簿」 (HP別途掲載)を添付 |
|
在留資格変更許可申請書 |
※申請前6か月以内に正面から撮影され た無帽、無背景で鮮明な申請人の写真 (縦4cm×横3cm)を貼付。写真の裏 面に申請人の氏名を記載。 |
|
特定技能外国人の報酬に関する説明書 |
第2表の1に該当する「一定の実績が あり適正な受入れが見込まれる機関」に ついては提出省略 |
|
特定技能雇用契約書の写し |
申請人が十分に理解できる言語での記 載も必要 |
|
雇用条件書の写し |
|
|
賃金の支払 |
|
|
申請人の個人住民税の課税証明書 |
1年間の総所得額、課税額、納税額が 記載されているものが必要 |
|
申請人の住民税の納税証明書 |
|
|
申請人の給与所得の源泉徴収票の写し |
複数枚の源泉徴収票がある場合は、確 定申告の上、税務署発行の納税証明書 |
|
申請人の国民健康保険被保険者証の写し |
申請時点で申請人が国民健康保険の被 保険者である場合に提出が必要 |
|
申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 |
|
|
次の①又は②のいずれか ①申請人の国民年金保険料領収証書の写し ②申請人の被保険者記録照会 |
申請時点で申請人が国民年金の被保険 者である場合に提出が必要 |
|
前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 |
前回申請時に提出すべきであった納税 証明書や納税緩和措置の適用に係る通知 書の写しなど |
|
公的義務履行に関する誓約書 |
- |
出典:法務省「「特定技能2号」に係る提出書類一覧表」参照
特定技能2号の取得方法
特定技能2号の取得方法は、以下のようになっています。
①特定技能2号評価試験に合格すること
②監督・指導者として一定の実務経験を積むこと
特定技能2号を取得するためには、
特定技能1号で実務経験を積んだ後に、特定技能2号へ移行できます。
特定技能2号は、求められる実務経験の分野により、
取得要件や試験内容が異なりますのでご注意ください。
特定技能取得にかかる費用

特定技能取得には、以下の費用がかかります。
特定技能1号取得にかかる費用
特定技能1号取得にかかる費用は以下の通りです。
|
費用 |
金額 |
|
在留資格申請費用 |
10~20万円程度 |
|
事前ガイダンス等 |
1.5~4万円程度 |
|
支援委託費用 |
1名あたり2~4万円/月程度 |
|
在留資格更新費用 |
4~8万円程度 |
|
健康診断費用 |
5千円~1万円程度 |
在留資格申請や更新手続きを、
登録支援機関や行政書士等に依頼する場合、別途費用が必要です。
健康診断については、就職前は外国人が負担、
就職後は企業側が全額負担となります。
特定技能2号取得にかかる費用
特定技能2号取得にかかる費用として、各分野の試験を受ける際の、
以下の受験料が必要です。
|
分野 |
金額 |
|
自動車整備業 |
4.800円 |
|
宿泊業 |
15,000円 |
|
漁業 |
15,000円 |
|
造船・舶用工業(溶接) |
96,800円 |
|
ビルクリーニング |
16,500円 |
|
農業 |
15,000円 |
上記以外に、合格証明書交付手数料が必要ですが、各分野の交付手数料が異なります。
特定技能1号から2号へのスキルアップの方法

特定技能1号から2号へのスキルアップの方法は、以下の通りです。
1年以上の実務経験を積む
特定技能1号から2号へ移行するためには、
1年以上の実務経験を積まなければなりません。
特定技能2号は、特定技能1号より高いレベルの技能が求められることから、
実務経験が必要になってくるのです。
業種ごとの試験に合格する
上記のように実務経験を積むためには、それにともなう知識も必要になります。
充分な知識を有しているかは、業種ごとの試験で計られるのです。
特定技能1号から2号に切り替えした場合の企業側のメリット

特定技能1号から2号に切り替えた場合の、企業側のメリットについてみていきましょう。
転職リスクが低い
特定技能1号から2号に切り替えた外国人は、実務経験や試験を乗り越えて、
その職に就いています。
自分が本当に就きたいと思っている仕事に就いているわけですから、
転職のリスクが低いのです。
5年以上の就労が可能
特定技能2号は就労期間に制限がないため、5年以上の就労が可能です。
ただし、建設、造船・舶用工業、農業、漁業、宿泊業、飲食料品製造業、外食業、
航空業、自動車整備業、製造業(工業製品製造業)、ビルクリーニング業に限定されます。
特定技能2号へのスキルアップにかかる費用

特定技能2号のスキルアップには、以下のような費用が必要です。
|
|
受験料 |
合格証明書交付手数料 |
|
工業製品製造業 |
15,000円 |
15,000円 |
|
ビルクリーニング |
16,500円 |
11,000円 |
|
自動車整備 |
4,800円 |
16,000円 |
|
宿泊 |
15,000円 |
12,100円 |
上記の費用は一例で、受験料は10,000円以上のものが多く、
合格証明書交付手数料は無料の分野もありますが、
上記のように10,000円以上のものもあります。
利用可能な補助金と申請方法

特定技能を受け入れる際は、受け入れ企業が費用負担しなければなりませんが、
費用負担は小さいものではありません。
そこで政府が行なっている
「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を
申請してみてはいかがでしょうか。
ここでは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)について
ご紹介します
(参照:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは
特定技能外国人を含む外国人労働者は、日本の法律や雇用などに関する知識が乏しく、
言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすいです。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、
外国人の事情に配慮し、外国人労働者の職場に定着に取り組む事業主に対して、
経費の一部を助成してくれます。
受給条件
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の
受給条件は以下の通りです。
(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(以下の1および2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
1. 雇用労務責任者の選任
2. 就業規則等の社内規程の多言語化
3. 苦情・相談体制の整備
4. 一時帰国のための休暇制度の整備
5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
受給額
上記の受給条件をすべて満たした場合、以下の受給額が支給されます。
|
区分 |
支給額(上限額) |
|
賃金要件を満たしていない場合 |
支給対象経費の1/2(上限額57万円) |
|
賃金要件を満たす場合 |
支給対象経費の2/3(上限額72万円) |
支給の対象となる経費は、以下の通りです。
(1)通訳費
外部機関等に委託をするものに限る
(2)翻訳機器導入費
事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限
り、10万円を上限とする
(3)翻訳料
外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するの
に要する経費を含む
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料
外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない
(5)社内標識類の設置・改修費
外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る
特定技能採用の成功事例

最後に、特定技能採用の成功事例についてみていきましょう。
外食業界の例
地方の観光地で、日本人2名で飲食店を運営していましたが、人手が足らず、
外食分野で受け入れ可能な特定技能外国人の採用を検討しました。
最初は、対面での面接での募集でしたが、なかなか人が集まらなかったため、
Web面接に切り替えたところ、全国から多くの応募がありました。
外食業界は人物重視での採用で、1名の採用を決めましたが、
その人の働く姿勢が良かったため、さらに採用枠を増やそうと思っています。
介護分野の例
介護分野は深刻な人手不足が進んでおり、
B社では、2019年の特定技能制度が開始されてすぐに、
特定技能外国人の採用を始めました。
特定技能外国人は、研修スケジュール・研修内容を自社で決めることができます。
支援はB社で行なっており、B社が考える教育・業務への姿勢を直接伝えながら、
24名(2022年1月現在)の特定技能外国人が働いています。
まとめ
特定技能1号・2号の違い、2号への切り替えした場合のメリットや費用、
補助金について、ご理解深まりましたでしょうか。
人手不足を解消する際は、特定技能外国人の採用を検討するのも1つです。
ただ、自社で特定技能外国人の採用手続きをすることに不安を感じている場合は、
運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
特定技能の登録支援機関の役割や仕組み、委託方法について徹底ガイド│委託せず自社で対応する方法も!
本記事を参考に、特定技能外国人の採用を検討してみてはいかがでしょうか。