
2030年になると、さまざまな社会問題が発生すると予測されており、
これを2030年問題といいます。
その社会問題を解決するために、政府、企業、個人は、
連携を図りながら対策を考えなければなりません。
本記事では、2030年問題について、詳しく解説します。
2030年問題とは何か
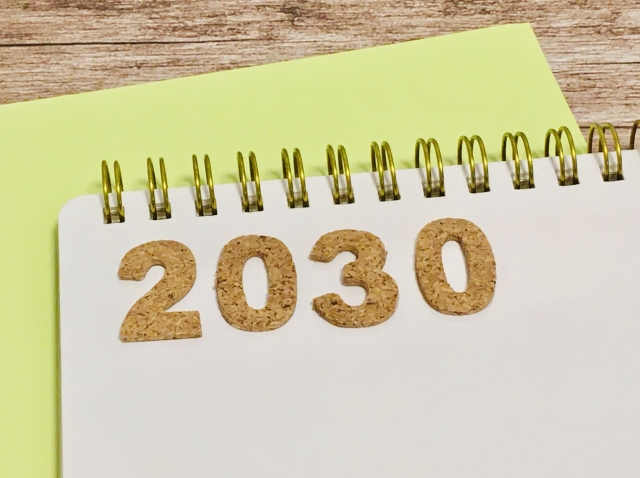
2030年問題とは、少子高齢化と人口減少が進行することで、
2030年頃にさまざまな社会問題が発生することをいいます。
では、具体的に、2030年問題についてみていきましょう。
2030年問題の背景
2024年現在の日本では、出生率が1.3、男女の平均寿命が80歳以上となっており、
世界的にも少子化・高齢化が進んでいる国です。
少子化が進行すると、生産年齢人口(15~64歳)が減少し、
企業の人材不足が加速することで、経済成長が大きく阻害されてしまいます。
生産年齢人口の中でも、特に若年層は都市部への移住が進んでおり、
地方の人口減少が加速することで、
過疎地域では地域経済や社会サービスが維持できません。
少子高齢化が進行することで、医療費や介護費といった社会保障費が増加し、
財政が圧迫されるほか、国民に対する税率が挙げられることも懸念されます。
また早くから発展してきた都市部では、インフラの老朽化が始まり、
維持・管理費が増加する一方、
インフラを整備する人材が少なくなってきていますので、
インフラの維持そのものが難しくなってきているのです。
このように、高度経済成長を成し遂げ、人口増加がみられた日本は、
のちに第3次産業が発展し、人口減少へと転じた結果、
2030年問題が起こり得る国になりました。
2030年問題が与える影響と課題
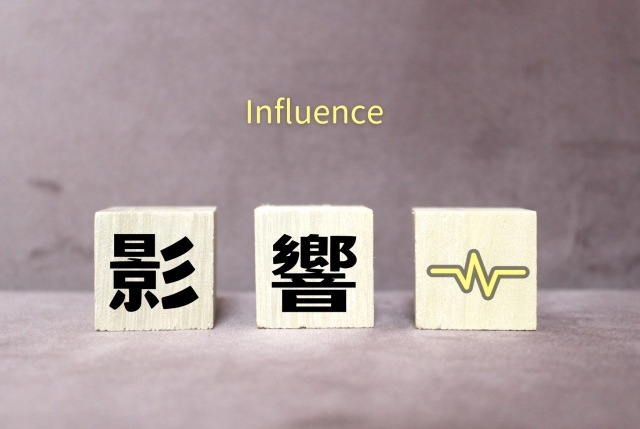
2030年問題が与える影響と課題についてみていきましょう。
人材不足が過激化
2030年頃にさまざまな社会問題が発生することを2030年問題とお伝えしましたが、
その背景にあるのが、少子高齢化です。
少子化が進むと生産年齢人口が減少し、
高齢化が進むということは
生産年齢人口超えた65歳以上の高齢者が増えるということです。
このように、生産年齢人口が減少することで、慢性的な人材不足が発生します。
運送業の人手不足については、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
【ドライバーの生の声】運送業の人手不足はどうすればいい?人手不足の原因や人手不足の解消事例も紹介!
AIと自動化の影響
上記でご紹介した人材不足はIT分野にも影響を及ぼします。
経済産業省「IT人材需給に関する調査」では、
日本のIT人材不足は約79万人に達しており、
その中でAIやデータサイエンスIoTといった専門家不足が指摘され、
2030年には約12万人を超える人材不足が生じると予測されているのです。
産業界全体で人材不足が予測されている今、
業界によってはAIや自動化を検討しているところもあるでしょう。
しかし、ITの人材不足が生じている以上、
AIや自動化にも遅れがみられる事態になりそう可能性があります。
人材費の高騰
2030年問題において、労働者不足を解消するために、人材獲得競争に乗り出しますが、
その際に、他社より高い人材費を提示して、人材確保を行ないます。
より優秀な人材を確保するためには、
さらに高い人材費を用意して人材確保に乗り出すでしょう。
このように、人材費の高騰は避けて通ることはできません。
物価の高騰
上記のように、高い人材費を捻出するということは、
企業はそれだけの収入を得る必要があります。
高い収入を得るためには、企業は商品・サービスの価格の引き上げを行ないます。
近年では、材料費等の高騰による商品・サービス価格の高騰もみられますので、
今後の物価の高騰は大きな影響を与えるでしょう。
外国人労働者との摩擦が起きる可能性
前述で、人材費の高騰について触れましたが、
会社がいう「人材」は日本人に特定しているわけではありません。
業績が伸ばすことができる人材であれば、外国人の雇用も視野に入れているのです。
日本人と外国人労働者が同じ職場で働く際、
文化の違い等から摩擦が生じる可能性は十分に考えられます。
摩擦が大きな問題になる前に、企業はその対策を検討しなければなりません。
外国人を採用するためのガイドについては、運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、合わせて参考になさってください。
特定技能の外国人を採用するための完全ガイド│職種一覧や採用方法、手続きの流れについても解説
2030年問題の影響を受けやすい職種
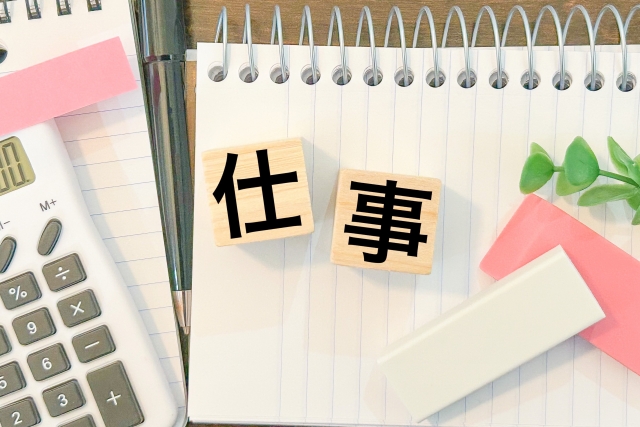
2030年問題の影響を受けやすい職種についてみていきましょう。
物流業界
物流業界の仕事は、労働時間が長く、
賃金が低いというイメージが持たれていることから、慢性的な人手不足が続いています。
求人ボックス給料ナビ「運転手の仕事の年収・時給・給料」では、
ドライバーの平均年収は406万円となっており、
日本人の給与所得者の平均年収の460万円(2023年)を大きく下回っています。
2024年問題でも取り上げられたように、
ドライバーの時間外労働時間の上限が、年間960時間に設定されました。
このように、現状でも物流業界では、人手不足が深刻化していますが、
少子高齢化により生産年齢人口が減少することで、
さらに大きな影響を受けることは必至です。
介護・医療業界
物流業界と同じく、介護・医療業界でも、重労働などに加えて、
賃金が低いという理由から、慢性的な人手不足が続いています。
求人ボックス給料ナビ「介護士の仕事の年収・時給・給料」では、
介護士の平均年収は325万円、
医療業界の一例として「医療事務の仕事の年収・時給・給料」では、
平均年収が341万円となっており、
いずれも日本人の給与所得者の平均年収の460万円(2023年)を
大きく下回っているのです。
今後、少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少すると、
大きな影響を与えることは言うまでもありません。
サービス業界
サービス業界の中でも、
とくに2030年問題の影響を受けると予測されているのは、飲食業や宿泊業です。
サービス業においても長時間労働が懸念されていましたが、働き方改革により、
労働時間を短縮する動きがとられたことにより、人手不足が顕著になりました。
前述の業界と同様に、
サービス業についても2030年問題の影響を受けることが予測されています。
IT業界
前述のように、IT業界では、日本のIT人材不足は約79万人に達しており、
とくに専門家は、2030年には約12万人を超える人材不足が生じると予測されています。
IT業界では、ITシステムの開発需要が高まる中、
スキル習得に時間を要することも専門家不足の要因となっています。
IT業界においても、2030年問題の影響を受けることは必至といえるでしょう。
企業がすべき対応策

企業がすべき対応策についてご紹介します。
労働力不足に対する戦略
労働者不足に対する戦略としては、まず既存社員のスキルアップを図り、
生産性の向上を図ることです。
また多様な人材を積極的に採用して、定着率を高めることも必要となります。
定着率を高めるためには、労働環境の改善や働き方改革を進めることで、
労働者の満足度を高めることが大切です。
さらに業務の効率化を図るためには、社員だけ業務を行なうのではなく、
アウトソーシングなど、
外部の人材の活用できる部分は業務委託するのも1つの方法といえるでしょう。
AIと人間の労働力のバランス化
AIが進展すると、人間の労働力を代替することが可能です。
AIは、定型業務や反復作業を自動化するのに役立ち、
労働者の負担軽減やヒューマンエラーの削減に役に立ちます。
しかし、現状でAI技術を導入するとなると高額な費用がかかりますし、
AIを搭載した機器は完璧なものではありません。
AIに任せられる部分はAIに任せてもいいですが、最終確認は人間がチェックするなど、
AIと人間の労働力のバランスが必要です。
自動運転の採用
物流業界では、自動運転が採用されることで、慢性的な人材不足の解消につながります。
2023年4月に道路交通法が改正され、日本国内でも特定地域のみですが、
自動運転レベル4の公道走行が解禁となりました。
自動運転レベル4とは、特定の条件下で、
すべての運転をシステムが自動で行なうことをさします。
2027年には、あらゆる条件下で安全に走行できる
自動運転レベル5の実証実験が計画されていますので、
今後の自動運転の採用に期待したいところです。
日本政府の取り組みと方針

日本政府は、2030年問題の取り組みとして、
高齢者の就労促進、少子化対策、デジタル化推進などの対応を考えています。
2030年問題の対応は、多岐の分野にまたがる課題に対応しなければならないため、
政府、企業、個人が連携して取り組まなければなりません。
政策立案と法整備
2030年問題に対応するため政府は以下のような政策立案と法整備を目指しています。
|
政府は、これらの動きを、企業の経営環境も考慮しながら進めていく必要があります。
まとめ
2030年問題について、ご理解深まりましたでしょうか。
少子高齢化が進むと、人材不足が加速し、全産業に大きな影響を与えてしまいます。
その影響を最小限にとどめるためには、さまざまな対策を考えなければなりません。
本記事を参考に、 2030年問題の解決に向けて、
行動ができる範囲で行動してみてはいかがでしょうか。