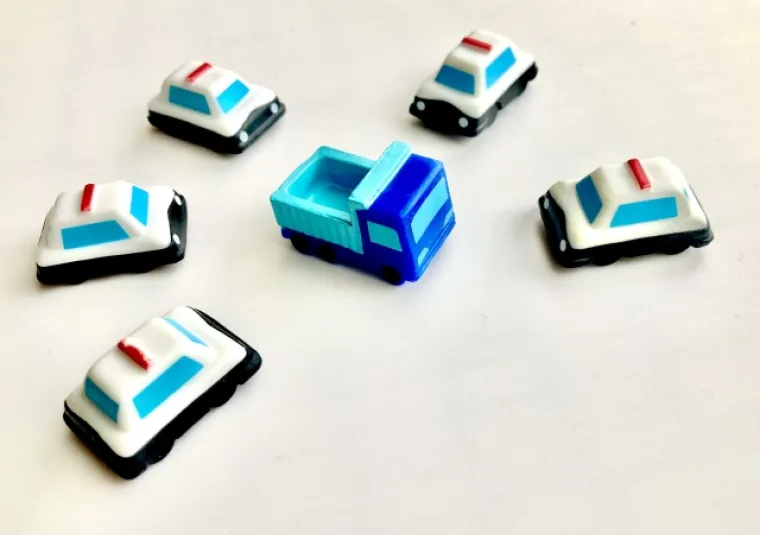
トラックに関する営業停止のポイントを説明します。
各種処分やそれに伴うリスク、具体例、事例、改正点などを押さえましょう。
営業停止の種類
言葉の意味どおりの「営業停止」となるのは、事業停止処分です。
この処分を受けると、所属する全ての車両が利用不可となります。
物を運ぶこと自体が禁止されるため、利益を生み出すことができません。
車両の使用が禁じられる車両使用停止(車両停止)と混同されることがありますが、こちらは別の処分です。
理解を深めるために、具体的な数値を見てみましょう。
国土交通省の発表によると、令和3年度の監査の実施件数は365件、行政処分等の件数は198件でした。
その内訳は車両停止が148件と最も多く、次いで文書警告が23件、事業停止が12件、所在不明を除く許可の取り消しが3件となっています。
このうち過積載通報処分は18件に上ります。
これらの主な違反内容は下表のとおりです。
【許認可(事業計画)等関係】
1位:事業計画認可事項(35.3%)
2位:報告義務(22.4%)
3位:事業計画届出事項(19.9%)
【輸送の安全確保関係】
1位:指導監督(25.3%)
2位:点呼(21.9%)
3位:過労防止等(16.8%)
行政処分とは
運輸局の監査で法令違反が見つかった場合、違反の内容や程度によって、営業所などに処分が科せられます。
運送会社に対する主な行政処分は次の3つです。
・自動車その他の運輸施設の使用停止処分(車両停止など)
・事業の全部または一部の停止処分(事業停止)
・許可の取り消し処分
■出典:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
各処分の内容を説明する前に、監査について簡単に触れておきます。
監査には、特別、一般、街頭の3種類があります。
これと関連するのが、トラック協会(貨物自動車運送適正化事業実施機関)による巡回指導です。
巡回指導によって処分を受けることはありませんが、場合によっては運輸支局に通報される可能性があります。
【監査の種類】
・特別監査:事故を起こしたなど、厳格な対応が求められるとき
・一般監査:上記以外のとき
・街頭監査:事業者を特定せずに運行実態を確認するとき 監査の実施方法は、臨店と呼出の2つです。
例えば次のようなときに、監査対象となります。
・法令違反の疑い
・死亡事故や悪質な違反の発生
・事業改善や巡回指導の拒否
・福利厚生の不備
・事故報告の未提出
・監査を長期間受けていない(対象除外の事業所を除く)
・一般貨物自動車運送事業の許可基準※を満たしていない
※参考:許可基準(一般)
車両使用停止
一定期間、車検証の返納と、ナンバープレートの領置が行われます。
これにより、当該車両が使用不可となります。
使用停止が科されるのは、例えば次のような場合です。
・休憩や睡眠施設の整備違反
・運行管理者の講習受講義務違反
・コンテナの落下防止装置未実施
・トラックの整備不良や不正改造
・タコグラフの記録改ざん
・酒酔いや酒気帯び乗務
■参考:「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」
車両の処分日車数の期間は、原則6か月以内です。
使用不可となる車両の数は、営業所に設置されている車両数に応じて決まります(最大で5割)。
下表のとおり、処分日車数や設置している車両数が多いほど、停止される車両数も多くなります。
■出典:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
事業停止
一定期間、違反のあった営業所での運送行為が禁止されます。
事業停止となるのは、次のような内容(重大な事故を引き起こすような悪質な違反)です。
・ドライバーの勤務時間や乗務時間の過度な違反
・全ドライバーに対して点呼を全く行っていない
・所属する全てのトラックに対して定期点検整備を全く行っていない
・整備管理者を選任していない
・運行管理者を選任していない
・名義貸し
・事業の貸渡し
・検査の拒否や虚偽の陳述 このほか、違反点数の累積(累積点数)によって対象となることがあります。
なお、下表に出てくる「管轄区域」とは、当該営業所と同一の地方運輸局(沖縄総合事務局を含む)のことです。
地方運輸局には、北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州の9つがあります。
■出典:貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について
【関連事例】
令和4年に発表された事例です。
大型トレーラーが踏切内で立ち往生し、列車の運転が一時見合わせとなった事故が発端となりました。
この事故の報道により2度の監査が実施され、定期点検整備の未実施をはじめ、タコグラフによる記録の不実記載、初任ドライバーや高齢ドライバーに対する指導監督違反、整備管理者の研修未受講など、複数の問題が見つかりました。
これにより、当該事業者の本社営業所に3日にわたる事業停止処分などが下されました。
許可取り消し
運送業の事業許可が取り消される処分です。
例えば、次のような違反によって許可の取消しが行われます。
・2年間に3回の事業停止処分を受けたうえで、上表(累積点数による事業停止処分)に該当
・同一管轄区域の累積点数が81点以上
・車両停止や事業停止、車検証の返納命令、ナンバープレートの領置命令に違反した
・事業停止処分を受けた事業者が3年間のうちに同一の違反をした
・命令(輸送の安全確保、事業改善など)に背き行政処分が下された事業者が、3年のうちに同じ命令を受け、その命令に再び背いた
【関連事例】
令和2年に発表された三重県の事例では、酒気帯び運転を伴う交通事故を起こしたことをきっかけに多くの違反が発見されています。
例えば名義貸し、点呼の未実施や不実記載、社会保険等の未加入などの違反事実が次々と確認されました。
これにより、33日間の事業停止や340日間の車両停止、文書警告が行われました。
しかしその後も改善が認められなかったため、2度の特別監査を経て、令和4年に許可が取り消されています。
行政処分のリスク

行政処分を受けることによって、経営状態の悪化や信用の失墜が懸念されます。
2019年4月に、事業許可取り消し処分が下された千葉県の運送会社の事例を見てみましょう。
同社はドライバーの乗務時間超過などにより、2018年に2度の事業停止処分が下されています。
その後改善が見られないと判断されたことで、累積点数が80点を超過したため、運送事業の許可が取り消されました。
なぜ改善されなかったのでしょうか。
経営状態の悪化
この会社が最初に書類送検されたのは2017年5月です。
労働時間を改善する意思を示していましたが、同年11月に再度書類送検となりました。
その後、会社に不安を感じたドライバーが次々と退職したことで、経営状態はさらに悪化します。
同社は400台以上の車両を保有していましたが、業界全体の人手不足も相まって、事業停止や車両停止の処分を受けた後に許可取り消しになったとのことでした。
信用の低下
さらに行政処分は荷主企業にも影響があるため、取引を失うことも考えられます。
3つの処分の中で最も軽い車両の使用停止でも、十分な輸送が行えなくなる可能性があるためです。
先の事例のように、行政処分によってドライバーが離職し、人手不足に陥ることもあるでしょう。
平成30年に変更された行政処分
平成30年7月に、過労に関する違反の処分が強化されました。
これは、当時の自動車運送事業のドライバーが次のような実態であったためです。
・労働時間が全職平均よりも約1~2割長い
・過労死の認定件数が職種別で最も多い
■出典:自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正しました
過積載に関する防止施策
平成25年11月より、過積載運行の処分が厳格化されました。
過積載を行った場合、1度の違反でも車両停止処分となります。
また、過積載を事業者が命じたまたは容認していた場合は、以下の内容のほかに7日間の事業停止が加わります。
■出典:近畿運輸局 京都運輸支局
過労に関する防止施策
平成30年7月に、過労防止に関する違反の処分量定が変更されました。
■出典:自動車運送事業者に対する行政処分等の基準を改正します~7月から過労防止関連の処分を厳しくします
まとめ
トラックドライバーの労働環境などを改善するため、行政処分の改正が繰り返されます。
処分を受けたことで経営状態が悪化し、改善がより困難となる可能性もあるため、問題点があれば迅速に解決を図りましょう。
なお、違反行為が荷主に起因する場合は「荷主勧告※」が発動されます。
こちらもあわせて確認しておきましょう。
※参考:荷主勧告が発動されやすくなります!