
人や貨物を有償で運ぶ場合、運送業許可の資格が必要であることをご存知でしょうか。
運送業許可の資格を取るためにはさまざまな条件に該当している必要があります。
本記事では、運送業を始めるための許可取得条件や、費用期間について、 詳しく解説します。
運送業許可とは

運送業許可とは、他から貨物を運ぶ依頼を受け、事業用トラックを用い、
依頼者から代金をもらって貨物を運ぶための許可のことです。
運送業許可を取得していない状態で、
依頼者から代金を受け取り、 貨物を運んではいけません。
運送業許可は法人で取得することもできれば、 個人事業主として許可を得ることもできます。
運送業の年収についてお知りになりたい方は、
運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、
合わせて参考になさってください。
運送業の年収を徹底解説!他社比較も!年収アップの方法や運送業界の将来性も紹介!
運送業許可の種類一覧

運送業許可の種類には、以下の3つがあります。
|
運送業許可の種類 |
内容 |
|
一般貨物自動車運送事業 |
荷主からの貨物を有償で運送 |
|
特定貨物自動車運送事業 |
特定の1つの荷主の貨物を有償で運送 |
|
貨物軽自動車運送事業 |
軽自動車・125cc以上の自動二輪で貨物を有償で運送 |
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、事業用自動車を使用して、
荷主からの貨物を有償で運送する事業です。
一般貨物自動車運送事業では、軽自動車の使用はできません。
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業は、1つの特定の荷主の貨物を有償で運送する事業です。
事業用自動車を使用し、貨物運送を行ないます。
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業は、荷主からの貨物を有償で運送する事業の1つです。
事業用自動車が軽自動車に限定されるか、 排気量が125cc以上の自動二輪車を使用して、貨物運送を行ないます。
運送業許可取得に伴う条件

運送業許可を取得する際は、 資金、人、場所、車両、法令試験の合格が条件となります。
運送業では、2024年4月1日より働き方改革関連法が施行され、
ドライバーの時間外労働時間(残業時間)の上限が 960時間を超えてはならないとなりました。
そのことも踏まえ、許可を取得した後は、 企業として労働者を雇い、労働環境を整えることが大切です。
法人の場合
法人が運送業許可を取得する場合は、以下の条件を満たしていなければなりません。
|
|
必要条件 |
|
1 |
資金計画が立てられること |
|
2 |
役員法令試験に合格すること |
|
3 |
運行管理者や整備管理者がいること |
|
4 |
5台以上の事業用自動車を有すること |
|
5 |
営業所の場所が、市街化調整区域内ではないこと |
|
6 |
農地法など、他の法令に触れないこと |
法人の場合は、役員法令試験に合格しなければ、
他の条件を満たしていたとしても運送業許可が下りませんのでご注意ください。
個人事業主の場合
個人事業主が運送業許可を取得する場合は、以下の条件を満たしている必要があります。
|
|
必要条件 |
|
1 |
貨物自動車運送事業法など、法律で定められた条件をクリアしていること |
|
2 |
開業後の6カ月間の人件費、12カ月間の事務所・駐車場賃料、自動車税・保険料が確保できていること |
|
3 |
事務所、休憩室、駐車場が確保できていること |
|
4 |
運転手5名、運転手5名、運行管理者1名、整備管理者1名が確保できていること |
|
5 |
事業用トラックが5台以上確保できていること |
|
6 |
運輸局で行なわれる法令試験に合格していること |
上記のものを用意するためには、ある程度の費用計算もしなければなりません。
経営者の適格性と関連法令知識
運送業許可の経営者の適格性と関連法令知識についてみていきましょう。
経営者の適格性
経営者は、運行管理者や整備管理者といった資格や、
その資格を有するための知識を有しているほど、適格性があるといえます。
関連法令知識を有する
運送業許可を得て業務を行なうためには、 様々な法令の知識を有しているほうが有利です。
運行管理者の配置条件
続いて、運行管理者の配置条件についてみていきましょう。
車両台数条件
トラックが1台から29台は1人以上、 トラックが30台以上の場合は2人以上配置しなければなりません。
営業所条件
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに運行管理者をおく必要があります。
事業計画の必要性と作成方法
事業計画書は、事業の見通しを立てるために必要であり、以下の内容を含めましょう。
事業の見通し
事業計画書の中には、以下のような事業の見直しを盛り込むのが基本です。
・事業を開始し、数カ月の月平均の売上高や必要経費を損益計算書として示す
・車両の減価償却費、租税公課、保険料などを計算する
・1年後、または軌道に乗った後の月平均の損益を記載する
現状整理
上記と合わせて、以下の現状整理を含める必要があります。
・運送業許可の取得状況
・運行管理者の資格
・整備管理者の資格
上記はあくまでも一例で、その他詳細を含めて現状整理をしてみてください。
車両の設備条件と基準
車両の設備条件と基準については、以下の通りです。
車両条件
車両条件の一例には、次のようなものがあります。
・車検証上の「貨物」の区分である「普通貨物車」「小型貨物車」が最低5台必要
・軽自動車や2輪車を含むことはできない
・自家用車を緑ナンバー車両にすることはできない
車庫条件
車両を保管するための車庫条件は、以下の通りです。
・すべての車両を保管できる広さがあること
・営業所に併設もしくは一定の距離内にあること
・車庫内は、車両相互間の間隔が50cm以上確保されていること
運送業務に必要な施設条件
運送業務に必要な施設条件には、次のようなものがあります。
新設要件
運送業の営業所・事務所を新設する際の要件は、以下の通りです。
・使用権限のあることを証明する書類が提出可能であること
・事務所、休憩室
・睡眠施設は車庫から10km以内(地域による違いあり。関東圏の一部で は20kmまたは5km以内)にあること
・建物が都市計画法、建築基準法など関係諸法令に抵触しないこと
運送業許可が必要な場合と不要な場合

運送業を始めるにあたって、運送業許可が必要な場合と、不要な場合があります。
どのような場合に、必要・不必要なのかをみていきましょう。
運送業許可が必要な場合
次のような場合のときは、運送業許可が必要です。
~ケース①~貨物輸送の依頼を受ける
例えば、企業などから輸送の依頼を受けた場合、有償で貨物を運ぶことになります。
輸送料などを得て、貨物を運ぶ場合は、運送業許可が必要です。
~ケース②~自動車輸送や引越しの依頼を受ける
積載車で自動車を輸送する場合や、引越しで荷物を運ぶ場合も、 有償で輸送することになります。
輸送料や引越し代金を得て、これらを運ぶ場合も運送業許可が必要です。
運送業許可が不要な場合
以下の場合は運送業許可は必要ありません。
~ケース①~自分(自社)の荷物を運ぶ
自分(自社)の荷物を運ぶ場合は、他からお金をもらうことはありませんので、 運送業許可は不要です。
注意すべき点は、自社のグループ会社の商品を「有償で運ぶ」場合は、 運送業許可が必要となります。
~ケース②~軽自動車で荷物を運ぶ
有償であっても、荷物を運ぶ際に軽自動車を使用するときは運送業にあたらないため、 運送業許可は不要です。
ただし、軽自動車を使用して運送を行なう場合、貨物自動車登録が必要となります。
~ケース③~自動二輪車で荷物を運ぶ
排気量125cc以下の自動二輪車を使用し、有償で荷物を運送する場合は、
規制がないことから運送業許可は必要ありません。
一方、排気量125cc以上の自動二輪車で、有償で貨物を輸送する場合は、
貨物軽自動車運送事業に該当すため、運送業許可が必要となります。
~ケース④~無償で荷物を運ぶ
貨物を運送する際に、お金のやりとりが発生していない場合は、 運送業にあたらないことため、運送業許可は不要です。
運送業許可の取得手続きや必要書類一覧

運送業許可の取得手続きや、必要書類についてみていきましょう。
必要書類一覧
必要書類は、以下の通りです。
|
|
必要書類 |
|
1 |
会社の登記簿謄本 |
|
2 |
会社定款写し |
|
3 |
残高証明書 |
|
4 |
決算書写し |
|
5 |
役員全員の履歴書 |
|
6 |
運送に使用する自動車の車検証写し |
|
7 |
営業所、車庫の平面図・配置図 |
|
8 |
営業所、借庫に車庫に関する土地建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し |
|
9 |
車庫前面道路の幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要) |
|
10 |
運行管理者の履歴書・合格証写し |
|
11 |
整備管理者の履歴書・資格者手帳写し |
|
12 |
貨物自動車利用運送を行なう際の契約書 |
|
13 |
営業所、休憩、睡眠室、車両の写真 |
|
14 |
社会保険に加入している証明書類 |
|
15 |
運転免許証写し |
申請の流れ
上記の書類を揃えた上で、以下の流れで申請を進めていきましょう。
~ステップ1~運輸支局・運輸局での書類審査
審査期間は約4~5カ月必要です。
~ステップ2~法令試験受験・ヒアリング
運送業に関する法令が出題され、正誤選択・語群選択方式の試験となっています。
~ステップ3~2度目の残高証明書提出
申請受付から約2か月後に提出しましょう。
~ステップ4~社会保険・労働保険加入・36協定締結
従業員には雇用保険にも加入させてください。 法定労働時間を超える時間外労働・休日出勤をさせる場合、 労働基準監督署への届出が義務です。
~ステップ5~運送業許可取得通知
法令試験合格し、運輸局の審査が終了すると通知が入ります。
~ステップ6~運送業許可証交付式・登録免許税納付書類取得
管轄の運輸支局で行なわれ、運送事業者としての説明を聞きます。
~ステップ7~登録免許税納付
12万円を金融機関に納付します。
~ステップ8~運行管理者・整備管理者選任届提出
運輸局保安課に提出しましょう。
~ステップ9~運輸開始前届提出
運輸局に提出します。
~ステップ10~事業用自動車等連絡書取得
自家用車で「車庫証明」にあたるものになります。
~ステップ11~緑ナンバー取得
ナンバー取得後、任意保険へ加入してください。
申請先となる運輸局の選定
運送業許可の必要書類の申請先は、 営業所が置かれている地域の管轄している運輸局になります。
許可の審査期間と内容
許可の審査期間は、以前は3~4カ月程度でしたが、
2019年11月の法改正により、審査期間は4~5カ月となりました。
審査内容については、以下の通りです。
|
|
審査内容 |
|
1 |
規模が適切であること |
|
2 |
使用権原を有していること |
|
3 |
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと |
|
4 |
申請者が車両を使用する権限があること |
|
5 |
資金の要件を満たしていること |
|
6 |
人の要件を満たしていること |
|
7 |
営業所の要件を満たしていること |
|
8 |
駐車場の要件を満たしていること |
|
9 |
車両の要件を満たしていること |
許可取得後の留意点
運送業許可取得後の留意点についてみていきましょう。
許可取得後1年以内に運送を開始しなければならない
運送業許可を取得してから1年以内に、運送を開始しなければなりません。
1年経過しても運送を開始できない場合は、運送業許可が失効してしまうのです。
ドライバーや運行管理者の確保など、柔軟に準備する必要があります。
運行管理者と整備管理者を選任しなければならない
運送業許可取得後、運送を開始する前に、 運行管理者と整備管理者を選任しなければなりません。
選任されなかった場合は、30日間の事業停止処分となりますのでご留意ください。
運送業許可取得にかかる期間や費用について

運送業許可取得にかかる期間や費用についてみていきましょう。
取得するまでにかかる期間
前述のように、運送業許可を取得するまでの期間は、約6カ月~1年です。
運輸局は、運送業許可の審査に約4~5カ月間かかると発表しています。
取得するためにかかる手数料や費用
運送業許可を取得するためにかかる手数料や費用は、以下の通りです。
|
|
項目 |
費用 |
|
1 |
申請手数料 |
第一種貨物利用運送事業の許可:9万円 ※船舶・航空・鉄道の場合12万円 産廃収集運搬業許可:81,000円 |
|
2 |
人件費 |
従業員の人数×6カ月分 役員報酬×6カ月分 社会保険等の金額×6カ月分 |
|
3 |
車両費 |
車両購入費用全額 リース・分割の場合は月々支払金額×12カ月分 |
|
4 |
車両関係の税金 |
自動車税・自動車取得税・自動車重量税×12カ月分 自賠責保険・任意保険の月々支払金額×12カ月分 |
|
5 |
車両関係費用 |
車両台数分の外注修繕費×6カ月分 タイヤ等の消費本数1本単価×6カ月分 月々総燃料1Lあたり価格×6カ月分 オイル代金×6カ月分×車両台数 |
|
6 |
営業所・駐車場 |
購入の場合は購入費用の全額 賃貸・分割払いの場合は月々支払金額×12カ月分 |
|
7 |
光熱費 |
光熱費×6カ月分 通信量等×6カ月分 |
|
8 |
その他 |
広告費用×6カ月分 必要設備にかかる費用の全額 |
運送業許可の更新と維持管理
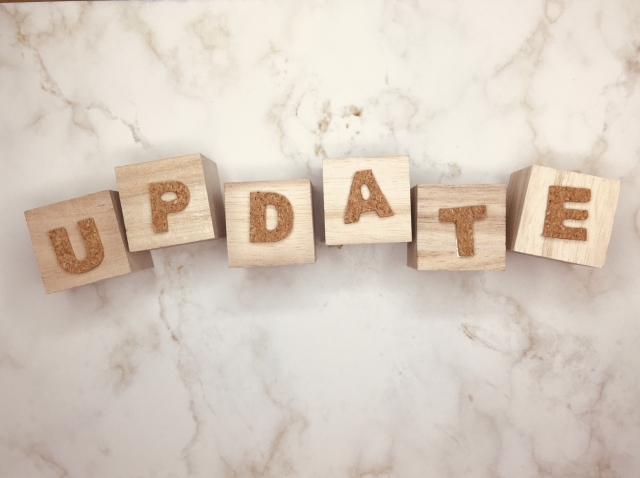
運送業許可の更新と維持管理についてみていきましょう。
許可更新手続きの概要
一般貨物自動車運送業許可に更新手続きはありません。
許可取消しなどにならない限り、運送業を行なうことが可能です。
ただし、営業所の場所や会社役員が変更になった場合は、 変更に関する申請を行なう必要があります。
また、産業廃棄物を運ぶ際に必要な「産業廃棄物収集運搬業許可」や、
貸切バス事業を行なう際に必要な「一般貸切旅客自動車運送業許可」については、
更新を行なわなければなりません。
定期的な点検
業務に使用する車両は、以下のように定期的に点検を受ける必要があります。
|
車両区分 |
点検時期 |
|
事業用トラック |
3カ月ごと 12カ月ごと |
|
バス、トラック、タクシー(事業用)、大型トラック(自家用) レンタカー(乗用車以外)など |
3カ月ごと |
|
中小型トラック(自家用)、レンタカー(乗用車)など |
12カ月ごと |
有償で人や貨物を運ぶ車両に関しては、
一般の乗用車・軽乗用車以上に、車両の点検整備に配慮しなければなりません。
点検整備を受けなければ道路運送車両法違反となりますのでご注意ください。
法令遵守のための内部監査
運送業において、適切に法令遵守が行なわれているか、 以下のような監査が実施されます。
|
監査 |
内容 |
|
内部監査 |
・社内の労働者などの内部監査機能をもつ部署が実施する監査 ・どのように監査するかの計画を立て、予備調査・本調査を行ない、調 査結果を評価・報告する ・監査手続き後の改善を行なう |
|
国土交通省による監査 |
・事故防止や法令遵守の調査を目的として実施される監査 ・安全確保に支障をきたす恐れがあり、法令に違反している疑いのある 会社から順に監査を実施 |
会社から順に監査を実施 監査の結果、違反行為があった場合は、
事業停止(営業停止)の行政処分を受けなければならない可能性があります。
違反点数の合計が51点~80点に超える場合、 その会社の管理区域内すべての営業所が事業停止となるのです。
許可取り消し防止のための取り組み
運送業許可取り消し防止のための取り組みとしては、
法令を遵守し、行政処分が科せられるような行為をしないことです。
上記のように、法令違反、悪質・重大な違反行為、
違反点数が51点~80点を超える場合に行政処分を受ける条件の対象となります。
運送業許可が取り消しになると業務を行なうことはできませんし、
処分から逃れようと自主廃業した際は、5年間の欠格期間の対象となるのです。
運送業許可は取り消しにならないよう、適切な業務運営を行ないましょう。
--h3: 業務改善や安全対策の実施 上記では、
運送業許可取り消し防止のための取り組みについてお伝えしました。
もし、運送業許可取り消しの対象となる運営が行なわれている場合は、
すぐさま業務改善を行なわなければなりません。
また運送業では、社員、顧客、貨物などを守るために安全対策の実施も必須です。
今一度、問題なく業務が行なわれているか確認してみましょう。
まとめ
運送業を始めるための許可取得条件や、費用期間について、 ご理解深まりましたでしょうか。
人や貨物を安全に運ぶために運送業許可の資格が必要です。
運送業許可の資格をとるためには、さまざまな条件に該当してなければならず、
申請の際の費用や期間についても理解していなければなりません。
これから運送業に就職をお考えの方は、 適切な業務運営が行なわれている運送会社を選びたいものです。
物流運送会社の平均年収や今後については、
運転ドットコムの下記の記事も役に立ちますので、 合わせて参考になさってください。
本記事を参考に、運送業許可について知っていただければ幸いです。